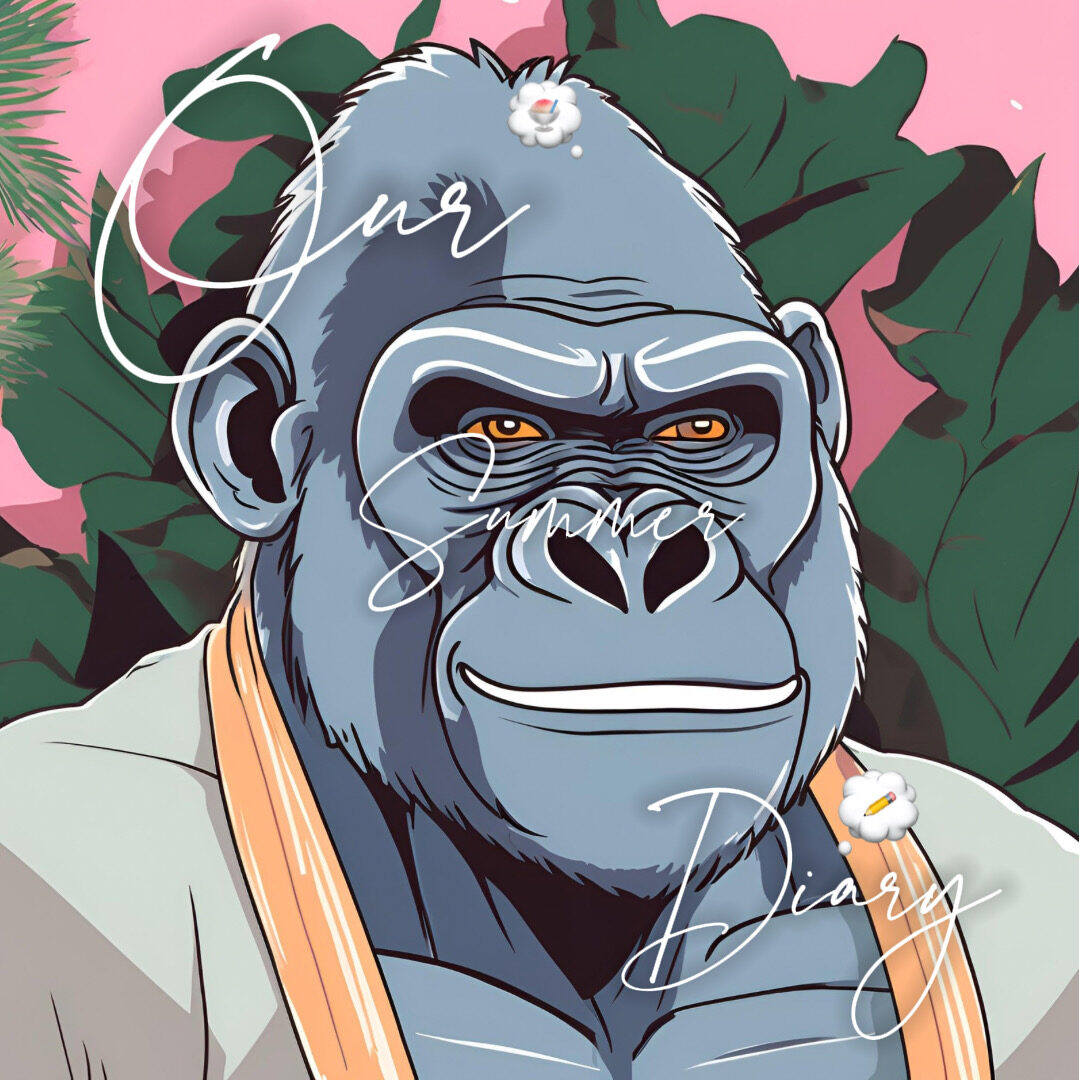皆さんは「不登校」という言葉に違和感を感じたことはございませんか?
不登校は一昔前、登校拒否という呼び方をされていました。(その歴史については後日)…登校拒否…確かにきつい言葉ですね。拒否?誰が?…子どもの責任という意味合いですよね。つまり、あくまでも「子どもの意思で学校へ行かない」ということになります。
それは違う。。。確かに「子どもが悪いわけではない」
詳細は割愛しますが、そこで生まれた言葉が「不登校」。現在では当たり前のように共通言語になっていますが、「不」これは打消しの語。否定する意味です。
意味合い的には「不登校」…学校へ行っていない打消し。否定。
私はこの否定的な意味合いやイメージを植え付ける言葉にずっと違和感を感じています。言って私も社会的に使うので偉そうには言えませんが、私の私見では、「不登校」という言葉は、世間的には、まだまだ子ども自身や家庭の問題と捉えられているのではないかと思っています。
一例ですが、例えば「学校外選択」など、子ども(家庭)自身が、主体的に学校以外の学びの場所を選んでいるという風潮を世間的に広げることができるのであれば、少なからずとも心理的に救われる子どもはいるのではないでしょうか。
不登校という負のイメージが世間体として、子どもを苦しめ、保護者を悩ませている。その負の連鎖が更に状態を悪化させる。前述したように「不登校」というカウント、ラベリングは学校の先生がしています。教育委員会がしています。自身や保護者が不登校と思っている以下に「不登校」としてカウントされていない可能性が高いです。
不登校約30万人。喫緊の課題!と叫んでいる学者さんや評論家さんのネット情報に踊らされ、お願いですから、とにかく焦燥感を高めないでください。その焦燥感が状況を良くない方向に進めてしまう可能性があります。
学校へ行っていない。学校へ行きたがらない。「なぜ?」…当然の感情です。
だからこそ一旦落ち着いて。社会にあるリソース(人材や機関等)を活用しましょう。
そして、活用される側は、プロとしてしっかり向き合って丁寧に合理的に支援してください。それぞれの役割には、プロとしての知見とスキルを学んだ自信がありますよね。
先生の免許は、大学を卒業したら自動的に取得できます。。。それで終わり??
「先生」と呼ばれ始めたら経験を積むだけですか?。。。教育者としてのエビデンスはどこで学ぶのですか。
先生(公務員)は、法の下で仕事をします。指導要領を読んでいますか?生徒指導提要を読み込んで教壇に立っておられるんでしょうね。