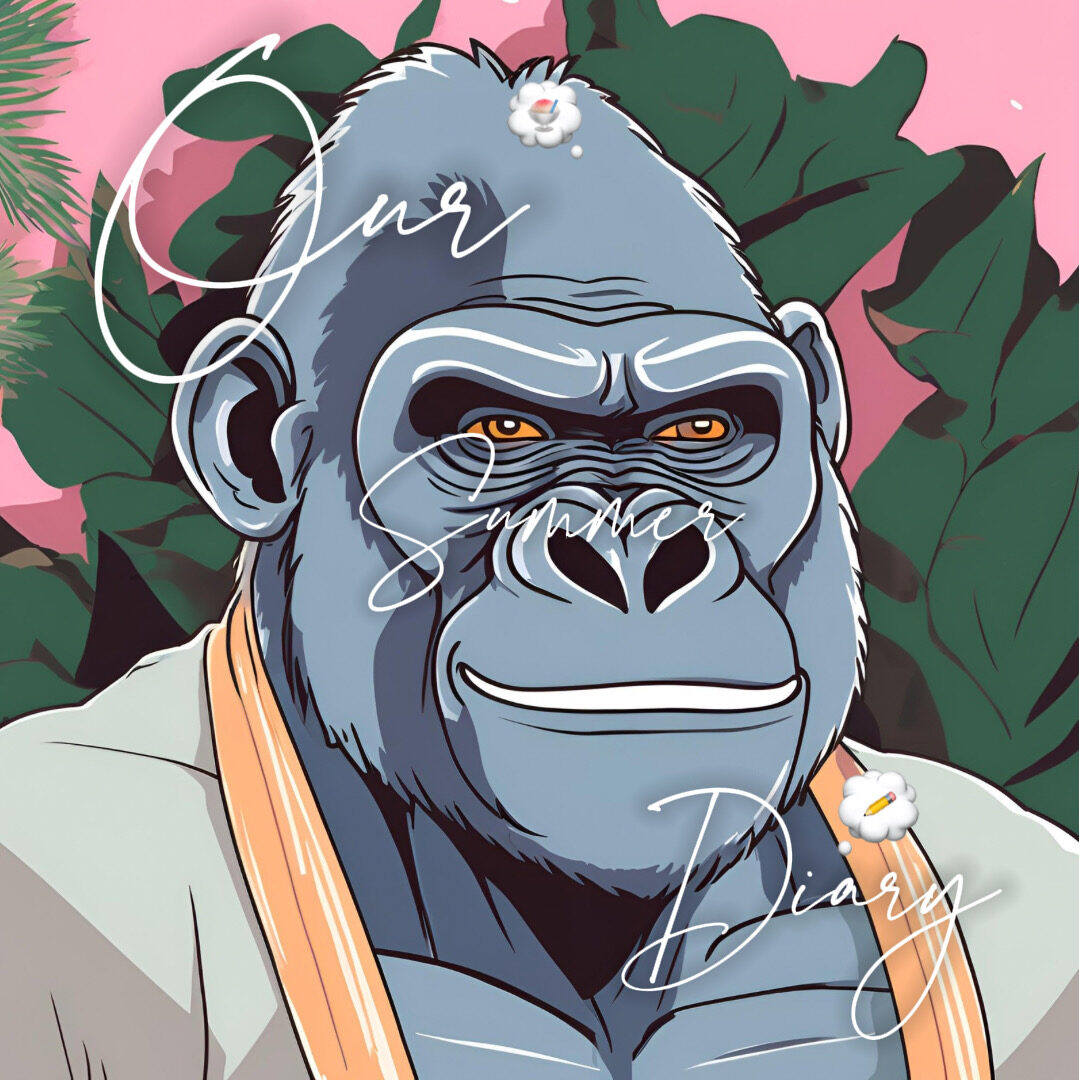「不登校の子どもそれぞれの状況…このブログではたしかに「不登校の支援」について注力していますが、今回に記事では、不登校であろうがなかろうが、「子どもそれぞれ」について書かせていただきたいと思います。
欠席29以内であれば、統計上「不登校」ではありません。そして、以前の記事で書いた「長期欠席」と「不登校」カウント、誰がどのように?誰の評価で?…等々、鑑みていただければ、世の中で騒いでいる「不登校約30万人」「10年連続増加」…
私見でご批判を頂戴するかもしれませんが、現在、その統計の仕組みど真ん中で働く私に言わせれば、疑問だらけで厳しく言うと既定路線です。しかし、学者さんや評論家等々、ネット内で論じられている数字はそれをベースに語られています。そりゃそうですよね。その数字に頼って論ずるしかないからです。でもこのブログを読んでいただいている方々は違いますよね。現実実態に目を向けてくださっていると信じています。
ごめんなさい。なにやら悪態をついているようで反省です。
本来述べたかったキーワードは「平等」と「公平」です。
公教育の中で、とある某A市の取組で「中学生の主張」というプレゼン大会があります。とあるB市では「ディベート教育」の推進というものを掲げておられます。
支援学級在籍(知的・難聴・言語・自閉情緒・肢体不自由・病弱・弱視)の児童生徒の参加する権利は?学力に困難さを持っている児童生徒の権利は?発達障がいを持っている児童生徒の権利は?様々な理由で学校へ行っていない児童生徒の参加するする権利は?
公教育ですから平等に告知はされていると信じたいですが、公平に参加することができるようなチャンスは与えられているでしょうか。また、一人ひとりそれぞれに適切なアプローチ(支援・配慮)はされているのでしょうか。
標準の子どもが見える風景について、身長が低い理由で見えない事実に対して、踏み台を用意してもらえているのでしょうか。
もちろん取組の是非を評価しているのではありません。得意分野を更に伸ばしてく仕掛けはとても有意義であると思います。しかし、大会形式にして競争させる必要があるのでしょうか?
その時間…自己肯定感を下げている子どもに対してどんなお得感のある学校生活の価値があるのでしょうか。
「平等」は、大人先導の企画に、みんな揃って「いっせいのうでっ!」
「公平」は、やる前に「これで嫌な気持ちになる子はいないかな?大丈夫かな?」って、子どもたち自身に考えさせる、考えてもらう時間と場所を設定することではないでしょうか。
私は「公平」を大切にしたい人間です。
みなさんはどう思われますでしょうか?