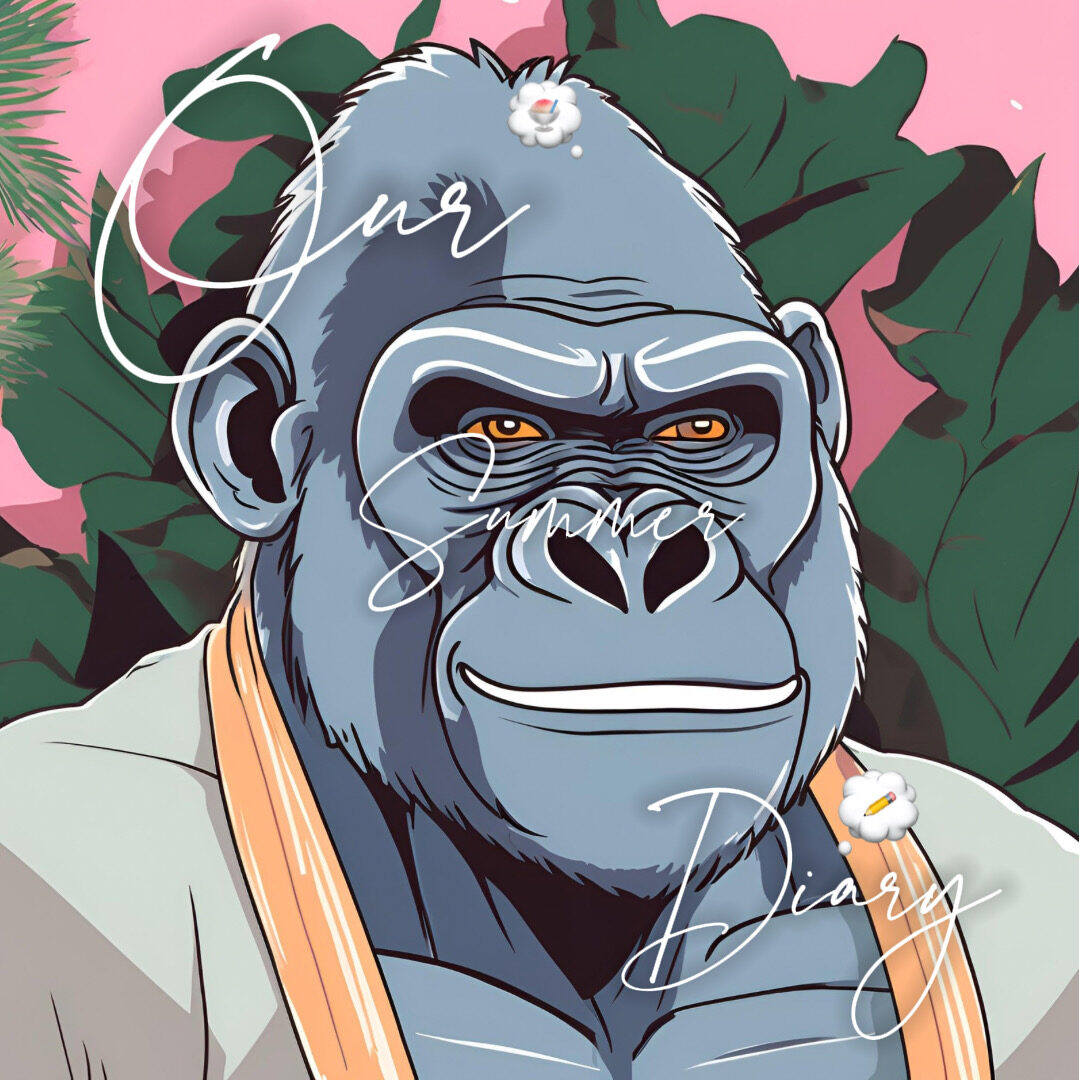中学校1年生から不登校状態。もちろん小学校から登校渋りはあったそうですが、いわゆる″小中間段差”による表出せざるを得なかったお子さんのお話。子のお子さんは一気に引きこもり状態となってしまい、ゲームに没入することで気を紛らわすことしか出来ず長期化してしまったそうです。食事もままならない、部屋からも出てこない、入浴も週に一度程度…その状態のまま、中学校3年生になっていました。もちろん学校も何も知ってこなかったわけではないと思いますが、結果として、引きこもり状態のまま現在を過ごしています。
私の行っているモニタリングで気になったので、中学校へ問い合わせたところ、家庭訪問は行っているが、最後に本人に会ったのが一年前。それ以降、本人に会うことができず母親と話をして帰校することが続いているとのことでした。心理状態を鑑みると慎重に対応せねばならないケースではありましたが、学校からのSOSもありましたので、母親と繋いでもらえることになりました。お母さんとの教育相談を重ねること数回、ある日、本人がこちらを見るだけならばということで来所してくれました。(課金をしてあげるという約束で連れてきたそうです)
瘦せており肩下までの長髪、口髭が伸びたまま真っ黒。目は合わない。狂気すら感じる雰囲気にうちの職員も通りすがりにかをを反らすほどでした。本人の心理状態をはかりながら、立ち話がいいのか着席した方がいいのか。いずれにせよ短時間にしようと思いました。初めは発語もなく目も合わない状態。お母さんは懸命に私とのコミュニケートを取らせようと必死。時間にして30分程度経ちましたか、これ以上はと思い、解放してあげようと話を持っていきましたところ、最後に「もういいですか?ありがとうございました。」と言葉を残して帰っていきました。
私の結論は「教育の領域を超えている」でした。「教育は万能なり」という信仰はとうに終結していると改めて感じさせられた面談でした。ではどうしたらいいのでしょう。福祉との連携なしではその子やそのご家庭は社会から取り残されていきます。学校は3年間どこにも繋がず抱え込んでしまっていたことに反省すべきです。虐待ではないから通告できない。だから?…地域のお力をお借りすることもあるはずです。民生委員さん、民生児童委員さん、他にも福祉領域には尽力いただけるリソースがあるはずです。学校がお約束事のように行っている「週一回家庭訪問」。本当にそれでいいのでしょうか。