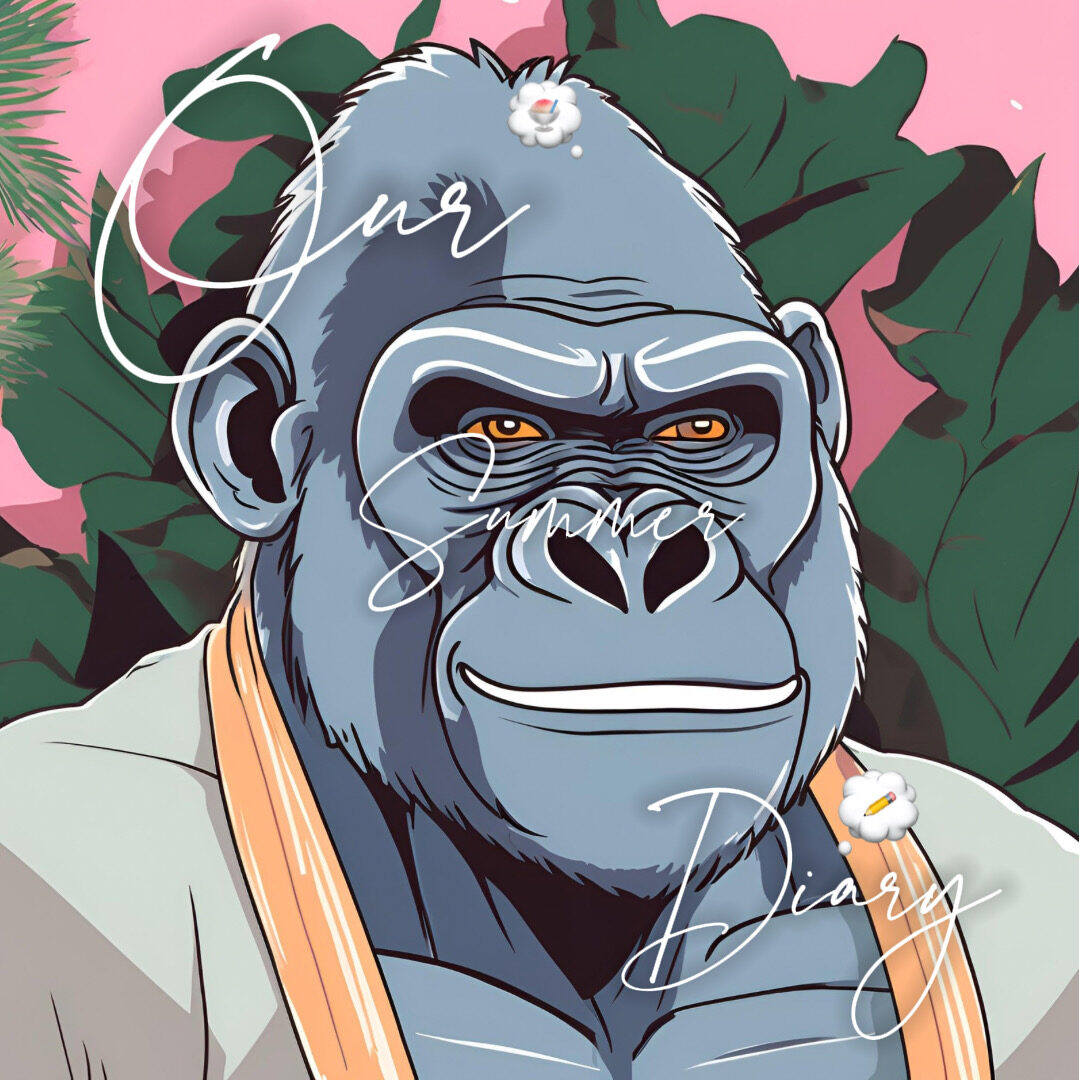「不登校」は「大人の無理解が問題」と活動している団体がたくさんあります。
それはどういう意味でしょうか?大人が要因となり、家庭内や学校内、地域、社会で子どもを追い込んでいる状態がいけない。だから、子どもが委縮したり困惑したりして、自由な行動が抑制されているという意味でしょうか。
この理屈から言うと、保護者や先生、子どもたちを受け止める社会が変われば、世の中が明るく変わる…という暗示ですよね。
根底に「大人が無理解だから、子どもがそうなるんだ」と、「不登校の状態」におられるお子さんや保護者の方々をカテゴライズされているのです。
だからこそ堂々と「一点集中型の価値観」を掲げて、団体活動を広めていけるのです。
まず一点目、「不登校は大人の責任」と言ってしまう発想。実はとても危険です。この反対言葉は「不登校は子どもの責任」です。
一昔前、「登校拒否」という言葉ありました。これは、子どもが学校を自発的に拒否する、あるいは、子ども内の何かしらの要因が、学校文化と不適応を起こしているので登校できない…という意味合いで長年用いられてきた単語です。しかし、違いますよね。この言葉は、「学校へ行かないのは、子ども自身の内発的な要因」、つまり「子ども起因だ」ということになるので、「登校拒否」という言葉は、この世の中から消え去り、大分と久しいです。(詳しく前述したので割愛します。)
では、「大人の責任」だろう。…という風に簡単に結論付けて、「不登校状態」を対局対局で、評論すること、唱ってしまうこと、世に広めてしまうことが危険です。それが「不登校」を活用した団体の怖いところなのです。時代の社会問題的に取りざたされている問題は注目を浴びやすいです。しかし、イデオロギーも確立していない者たち(団体)が、外野から口出しすることは是非止めてほしいと願っています。ましてやお金儲けの手段にするなど以ての外です。
何かしらの出会いがあり、言い出すことは自由です。しかし、マスコミ(社会問題ネタとしてのターゲット)や社会的影響等を鑑みて、自身のイデオロギーが未成熟であるのであれば、オファーを辞退願いたいです。
不登校をキャンペーン化するのは止めてください!!
なぜなら、当事者にとっては繊細な課題であり、当事者が仮に30万人おられるのであれば30万通り(すべて異なる)のお悩みがあるのです。
我々、教育・福祉・心理・医療の分野の専門家から言わせると「お祭り騒ぎで当事者を惑わさないでいただきたい!」です。
いじめの構造と似ている構造もあるのです。
「過去、自分が不登校だった…」「過去、うちの子も登校拒否だったけれど、ここと出会って立ち直った…」的な。
つまり、「今は被害者ではありません」
あとは、冒頭からお話している「観衆」です。…いっちょかみですが、「応援しています!」「がんばれ!」「大人が変われば子どもも元気になる!」…みたいな……(これが実は一番たちが悪い)
あとは最後に「傍観者」です。・・・さて、この立場は、どんなひとたちがあたるのでしょうか?皆さんも考えてみてください。
長くなりましたが、大きな二点目。
最も優先されるべき、子どもの気持ち(心理)は、どこへ行ってしまったのでしょうか。
仮に、惑わされてイベントに参加したご家庭があったとしましょう。それを「よかったよ~」と漏れ聞いた子どもの心のやりどころはどうしたらいいのですか?「みんなで楽しみましょうよ」…素晴らしい心構えであるとは思います。でも、参加できない…参加したくてもできない…参加させたくても参加させれない…そんなご家庭のことを、少しでも想起されたことはおありですか?
学校も似ていますよね。もうすぐ運動会!体育大会!文化祭!…学級旗をみんなで作成したりして、楽しいですよね。・・・でもその時、あの子は、あの親御さんは?…
先生自身の心理の中で、想起されて本当のウオンとに沿ったフォローがなされていますでしょうか?
教育は万能なりではありませんよ。