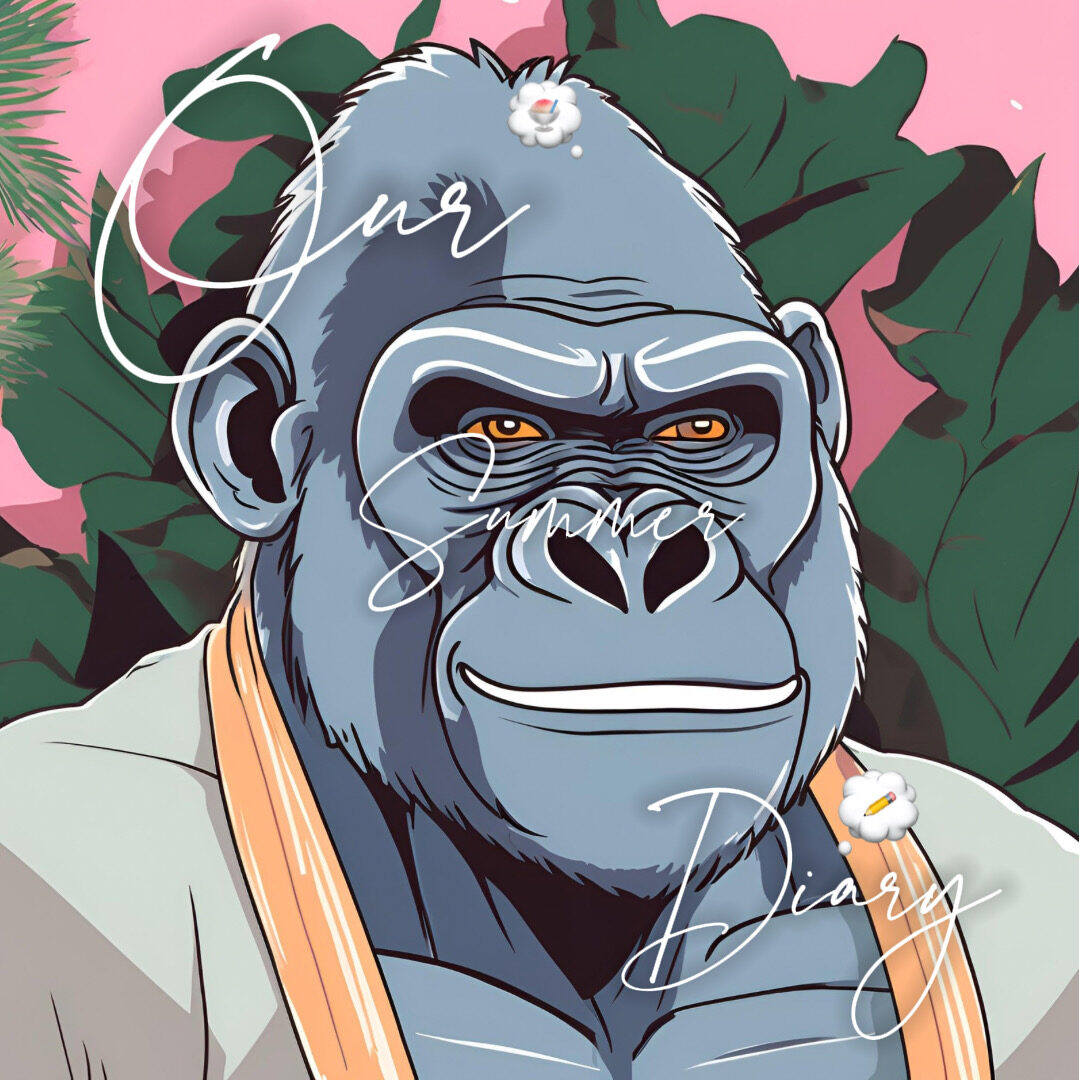先日、学校訪問する際、校門の前で泣き叫ぶ子供の声…
手を引っ張り校門へ入れようとされているお母さん。子どもになにやら語り掛けてなだめようとされている先生。静止すると下を向いて涙を拭くお子さんですが、大人がアクションを起こすと途端に泣き叫ぶの繰り返し。
お母さんや先生のお気持ちもよく理解できます。(その後のスケジュールもありますし…)しかし最も最優先されるべきことは、そのお子さんの心模様ですよね。子どもの事情です。
子どもの中には、少数かもしれませんが現実的に、学校に不自由さ(不必要さ)を感じ、自ら学校という選択肢を外す「積極的な不登校」の子どもいます。しかし、ほとんどの子どもは、友だちや先生との関係でうまくいかない、過敏、大集団での不適応等の理由で学校に行くことが出来ず、自らに深い罪悪感を感じています。
「なんでみんなと同じことができないんだろう」「自分はダメな存在なんだ」と、自分を傷つけてしまう子どもたち。(本当は大人のせいなのに)
そんな子どもには、是非、まずは「あなたは悪くない」「あなたがおかしいんじゃない」「大丈夫」と見守り、支える大人の存在と出会わせてください。お母さんがすぐに出来なくてもいいんです。ピンチヒッターでもいいんです。逆に言うと、混乱されているお母さんに「落ち着いて」「大丈夫」「どっしり見守ってあげて」と言っても土台無理な話です。社会のリソース(資源)を活用するよう視点を変えてください。
愛着対象はピンチヒッターでも大丈夫です。お母さんが一旦、休息をとってください。
親子の愛着がピンチヒッターに負けることはありません。
「保護者の役割はとても大きい」というセンテンスをよく耳にされると思いますが、「保護者が全てです」とか「保護者の責任は大きい」という意味ではありません。そういう勘違いしたインプットをしてしまうと場がびくケースが多いです。専門家だけではなく、ママ友でもいいと思います。私が関わらせてきた沢山のお母さんにお聞きすると、ママ友とのランチ、お茶タイムもとっても大きな意味があることが多いらしいですよ。
さて、先生はいかがでしょうか。
「私がなんとかしてあげる!」「私に力量がないから…」と力んであられませんか?
同じことですよね。
学級経営最優先で学校に来ていない子は二の次と思っておられる先生はお話になりませんが…