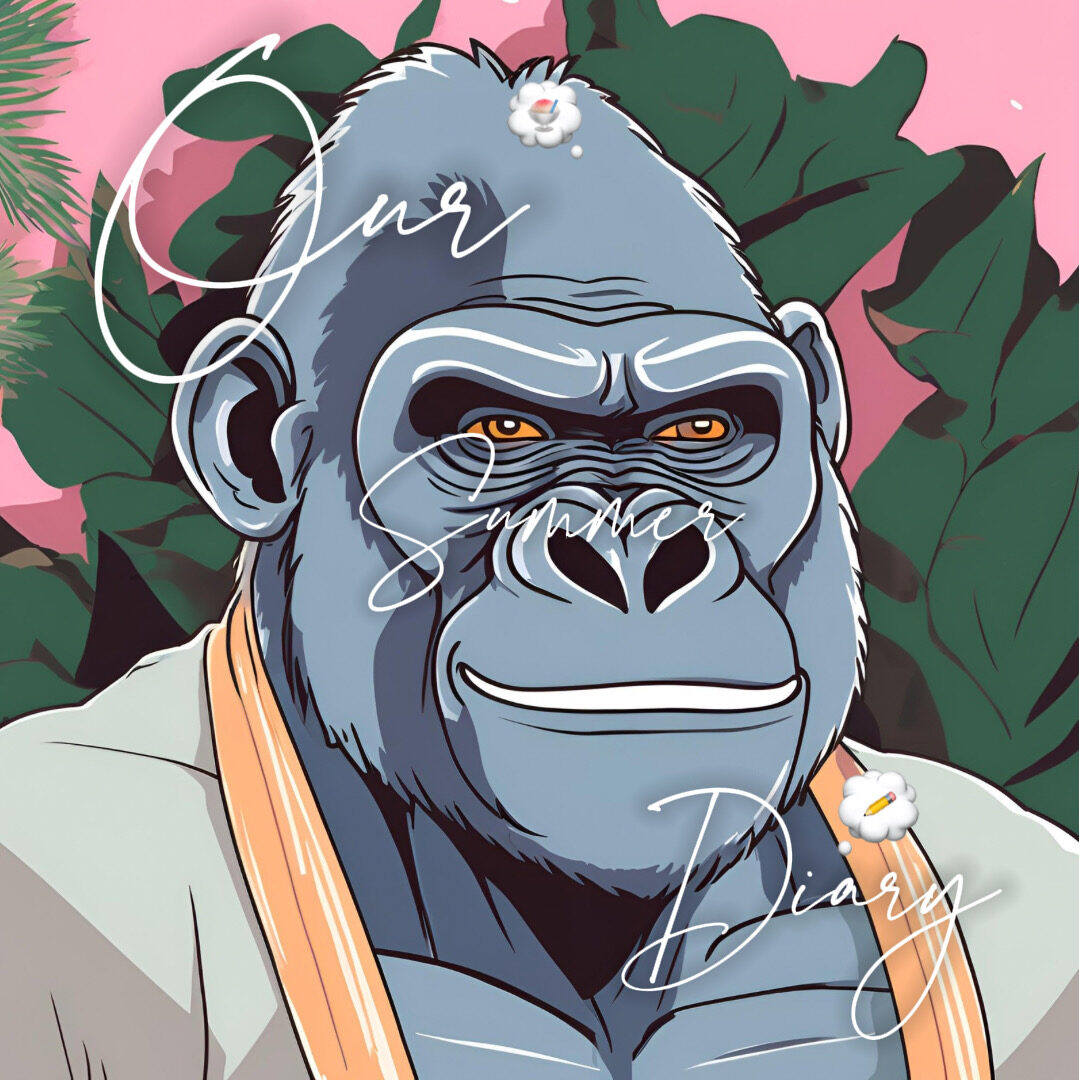不登校状態の始まり“登校渋り”。不登校状態の低年齢化を少しお話ししましたが、直に我が子から「学校に行きたくない…」とつぶやかれたら、本当に焦りますよね。大人は見通しがもてる(先が負に見える)ので、「ここをなんとか踏ん張らなくせては!」と必死です。
現代あらゆるところで取りざたされている「不登校」。極端な話、「=引きこもりの大人になる」みたいな不安。引きこもりの状態が是か非かの話は、少しだけ前述しましたが、ここでは置いておいて、不安感や焦燥感、緊張が家庭内に高まることは、親として当然の心理現象であると思います。
どこかで語る「不登校論者」(私も一部そう思われるかもしれませんが…)
「焦らなくていいですよ。」「本人が動くまで待ちましょう。」・・・
いやいや、家族(当事者)の初期の心理状態は、とても待てるものではないですよね。うちもそうでした。
先週お受けした相談のお母さんも焦っておられました。何度も言いますが当然です。
そこで、初回、1時間お話をお聞きした上で「取り合えず待ちましょう。」「今は焦らないで。」「お母さんの心理状態が伝わってしまうので。」…そりゃないですよね。
私が心がけるのは、イメージとして、100%傾聴しているようで、同時進行でその内、アセスメント(見立て)に40%、プランニングに40%、方向づけに10%、次回へのつなぎに10%のエネルギーを使います。
つまり、お母さん曰くの情報だけではわかりません。まずは、お母さんの見立てをしたうえで、お母さん支援をスタートさせていただきます。これが80%。
ご本人に新たな気づきを持って帰っていただかなければ継続できませんので20%のエネルギーを要するということです。
心理士のマニュアル通りに「待ちましょう」「落ち着いて」…。それでいいなら誰も来ないでしょ。
お願いですから、ネット上で「不登校専門家」等々とコラムを書いておられる評論家や大学関係者の方々の、一片を切り取った情報に迷わされないでください。よく読んでください。良きアドバイザーが書かれている文脈と文末を。…きっとそこには、「よくあるケースとして…」とか「検討してみてください…」など、伝わってくるはずです。(数字で断定している学者は論外。またその数字を操作している人間は大論外ですけど。)
さて本題。
判断は、子どもの発言そのものです。身体症状そのものです。
で、最も近しい絆あるサポーターがするべき行動は、何人探しをして叩きのめすことでも、ODだから仕方ないとして服薬に頼り続けることでもない、「中・長期プラン」を立てることです。
そして一言だけアドバイスさせてください。「おひとり」「家族内」のみならず、良き専門家をより多く社会的資源(リソース)として活用する仕組みを構築するよう、そちらにもエネルギーを使ってみてください。
怒りのエネルギーは枯渇します。サポーターが枯渇しては最たる主役に勇気が出ません。
一度ご検討くださると幸いです。