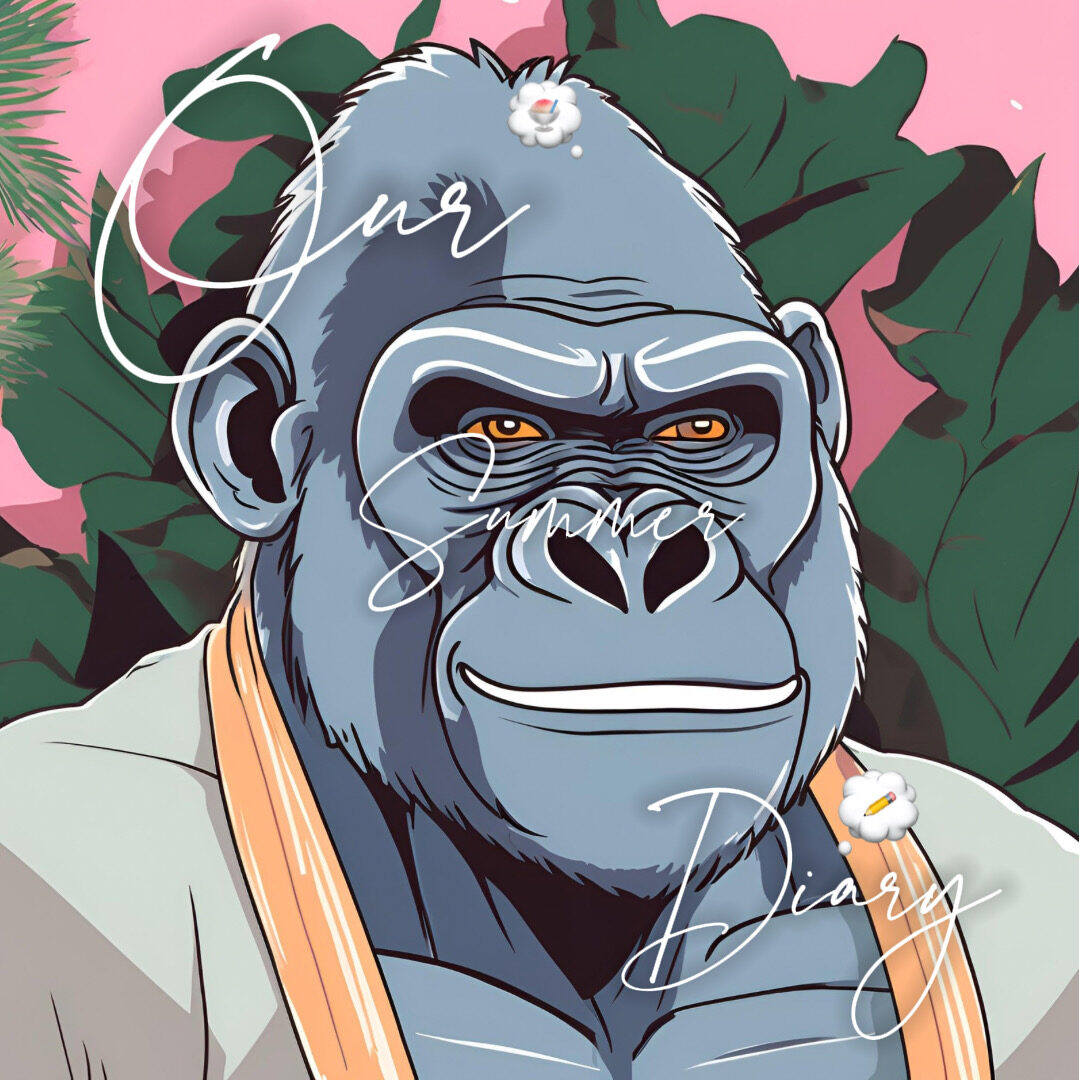学校の役割は「学習」と「コミュニティ」。この二つを他で補えるのであれば、学校へ学校へ行かなくてもいいですよね。
二つの機能を「学び」と「成長」あるいは「自立」という言葉に置き換えるのであれば、フリースクール等の民間施設や民間団体、極論、親御さんが関われるのであればご自宅でもいいんです。つまり、学校以外でも「成長」することはできるのです。
とはいえ、学校を否定しているわけではありません。私自身も過去、教壇に立っていた身として「不登校状態のお子さん」に「学校復帰」を願っていました。(当時は、法整備もなくそこに注力する法人も少なかったですが…)
学校には行かなくて「も」いいという考えです。不登校は選択肢の一つ。学校へ行きたい子は学校へ行けばよい。学校へ行かない子は学校へ行かなくてもよい。問題は、学校行きたいけれでも行きにくい子どもの存在です。行かねばならぬのに行けない。登校することを重圧と感じ自分を責めてしまう子どもの存在です。だれの価値観で生きているのか?生かされているのか?何を求められているのか?…考えさせられてしまいます。
「自分は自分の主人公」のはずです。
子ども自身が学校へ行きたがらないのであれば、無理に行かせる必要はありません。不登校の状態にならざるを得ない要因は千差万別です。机上で勝手にアセスメントしたような感じになり、人の人生をなんとなくプランニングしないでください。学校はそのような「作業」を「ケース会議」として行っています。もちろん、「その子どもを救ってあげたい」…気持ちは尊いですし、ありがたいです。しかし、その会議に居ない子どもの「現在の心理状態」に本当に耳を傾けておられますか?心は止まりません。先述したとおり、不登校状態のお子さんほど、心のスピード感は速いものです。先生方が、他業務を多忙に繰り返しされている正にその時もその子の心は波風高く動いているのです。先生を責めているのではありません。先生の体も一つしかありませんので。
では何が…あえて言いますが「人材」「時間」「場所」…つまり、教育予算です。各自治体によって差異はありますが、ご自身の住まわれている自治体の予算の中で「教育予算」がとれだけ使われているかご存じですか?丁度、9月ですので「令和7年度予算議会」が行われる時期です。
誰のための予算決議でしょうか。
子どもに投票権はないのです。
大人は仕事や生き方、投票もそうです…自分で選べますよね。…子どもはいかがですか?
そして、困っているお子さんを抱えていらっしゃる保護者の声は自治体や国に本当に届き相手にしてもらえているでしょうか?