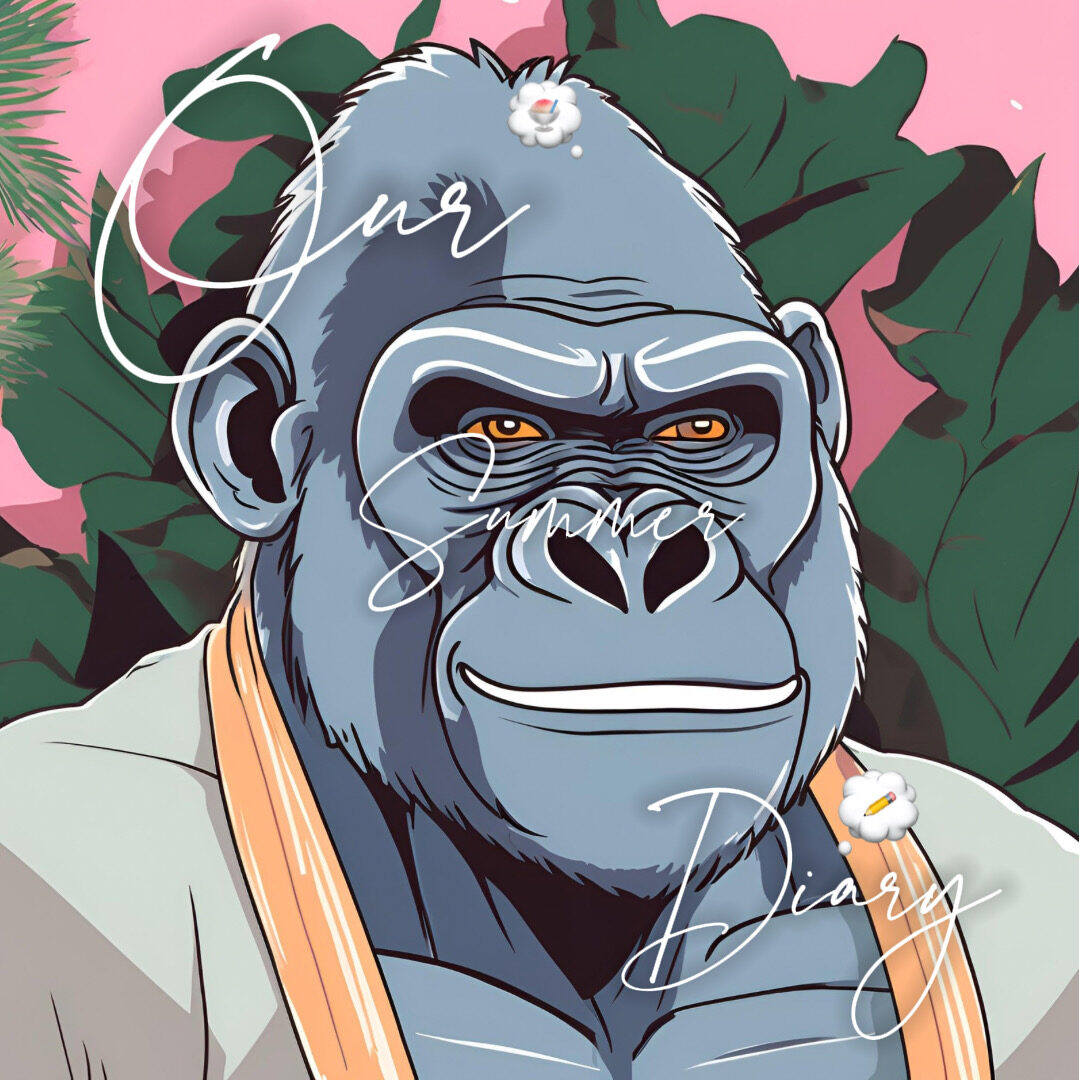「答えは子ども自身の中にある」が答えです。
人は自ずと成長しようとする生き物です。ちゃんとやりたい事や夢、理想像を見出していきます。ここで問題なのは、周囲とのスピード感のズレです。
当事者本人が困惑中、焦りと不安。誰が決めたか邪魔をする“現代日本の普通”とかけ離れていく自分への苛立ち。本人が一番わかっているのです。
親として…我が子の登校渋りが始まり、ゲームや動画に没入し、生活リズムが崩れ始めていく…。良かれと思い言葉がけをすると、反抗的な言動……理解したくとも、我が子とは言えども別人格。本人の心の動きがどんどんわからなくなってしまいますよね。親心として本当に苦しいですよね。
心理士に相談すると「待ちましょう」…そりゃないですよね。
いつまで?待つだけでいいの?家庭の中でリアルにずっと我が子を見続けている親の気持ち。
助けてくれるの?…「誰か結果を出して!」って叫びたくなりますよね。
私は、「待ちましょう派」ではありません。
ご相談をお受けする数多のご家庭において、100ケースあれば100通りの支援策を模索します。当事者意識を優先して。すべて「他人事」から「自分事」に取り込みます。魔法使いではないので急変させる術など持ち得てはおりませんが、どの領域が有効か?大きなチーム編成がいいのか?小さなチーム編成がいいのか?またその人材(リソース)は?タイミングは?・・・頭が爆破しそうになるくらい考えます。平静を装って。
少なくとも、相談に来られる方々は「方針」「方向性」「技」等を求めに来られていると思っています。だから、一辺倒な「待ちましょう派」ではありません。
少し話が逸れてしまいましたが、例えば「昼夜逆転」。
学校へ行きたくとも行けない本人にとっては、昼の時間帯は、罪悪感に襲われる時間帯でもあるかもしれませんね。だから、何かしらに「没入」しておかなければ心が保てないのかも。以前お話ししたかもしれませんが、不登校の状態にある子どもほど、学校を人一倍意識しています。そして時間が長い。自己否定や自己嫌悪、罪悪感に襲われてしまうので、夜の方が安心できるのかもしれませんね。
ODの診断が出たから…とか、基本的に放っておけば大丈夫…などと乱暴なことを言うつもりは到底ありません。
もちろん状態を見つつですが、「明日の朝ごはん〇〇にそようかな?一緒に食べてみない?」など、ポジティブな声掛けをしてみるのもいいかもしれませんね。
中学卒業後、進学が全てではありませんし、あまりデータは好みませんが、中3で不登校を経験した子どもの約85%が高校に進学しているというデータがあります。
このデータをどのように捉えられ方は各々違うと思いますが、どのようにお考えされましたか。