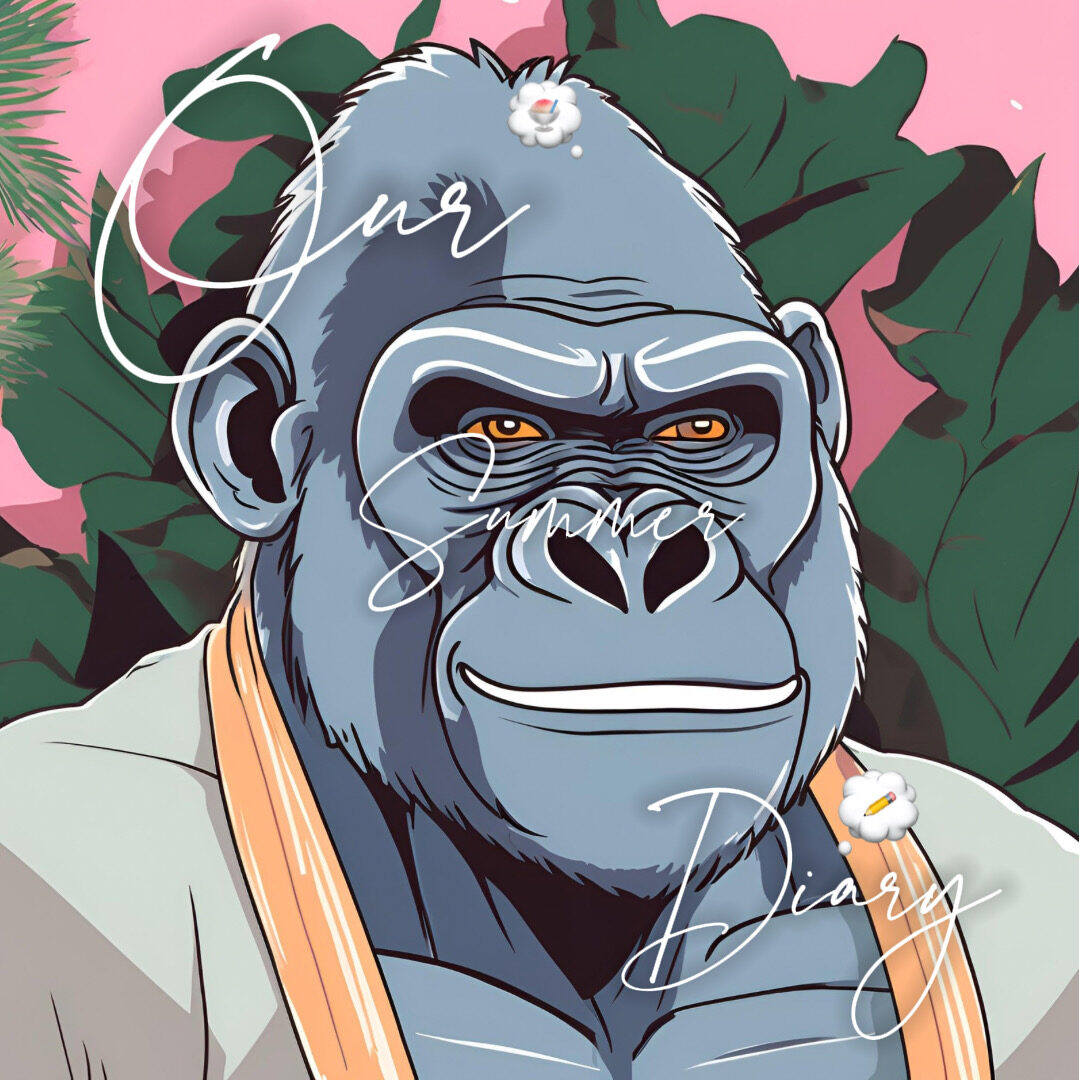「不登校は問題だ…」
日々、不登校状態におられる親子のご相談やサポートをさせていただいている私の体感ですが、現代日本の不登校に対するイメージは99%が、個の価値観に囚われ苦しんでおられます。
教育機会確保法があるとは言えども、まだまだまだまだ容認されていない状況です。国や自治体がいくら法整備や環境調整をしても、先生方が支援方法を変化させても、未だ「普通じゃない」扱いです。5年後?10年後?15年後?…いつになれば、何が変われば、国民の価値観は変化して、この多様性を認め合える時代が来るのでしょうか?
私が出会わせていただいている方々も、どこかでこの価値観に苦しめられ、故に子ども自身が更に二次被害を受けている。成長とともに社会的自立へ向かうとはいえ、誰も保証してくれません。親心は「いま」をなんとかしてほしいのです。おっしゃる通り。ごもっともです。
旧態依然とした教え込み教育に変化を促進しようとする教育委員会。しかし、一方で不登校状態にいるお子さんにとっては副作用が生じることも。重要なことは、「教育がどこを軸足に仕事(役割)をするか」であると思います。
「誰一人も取り残さない教育の推進」…きれいごとをキャッチフレーズにして、英才教育は止めてほしいものです。
発達障がいは「脳の個性」です。
個性を大切にするというキャッチフレーズと国の方針との乖離。矛盾することは必至です。
では、「モンテッソーリ教育」や「イエナプラン」、「シュタイナー教育」等を推進する「オルタナティブスクール」も「普通の選択肢」にまで広告してください。補助助成してください。
結局、公教育は「民間との連携は必須」と謳いながらも、公教育と民間教育との差別化を図りたいのです。
先見ある有望な教育者は既に気づいているのです。
だからこそ「教員不足」
退職された先生方をも巻き込み「非常勤教諭」の争奪戦。その方々には、もう退職金を支払う必要がありませんから…。若く有能な先生が「正規採用」すると、一人約3億円の未來投資。
どれだけ未来の宝である子どもたちに投資しない国なのでしょう。
年金を先延ばしにして、老後資金をためようとしている年配の先生方を批判しているわけではありません。経験と知見でお力のある先生が多数と信じたいです。
しかし、教師として生き抜いてこられた中で熟成された不登校への価値観は往々にして変わらないものです。
なんなんですか?再任用校長って。少なくとも校内で若い新しい価値観の邪魔をしないでほしいものです。