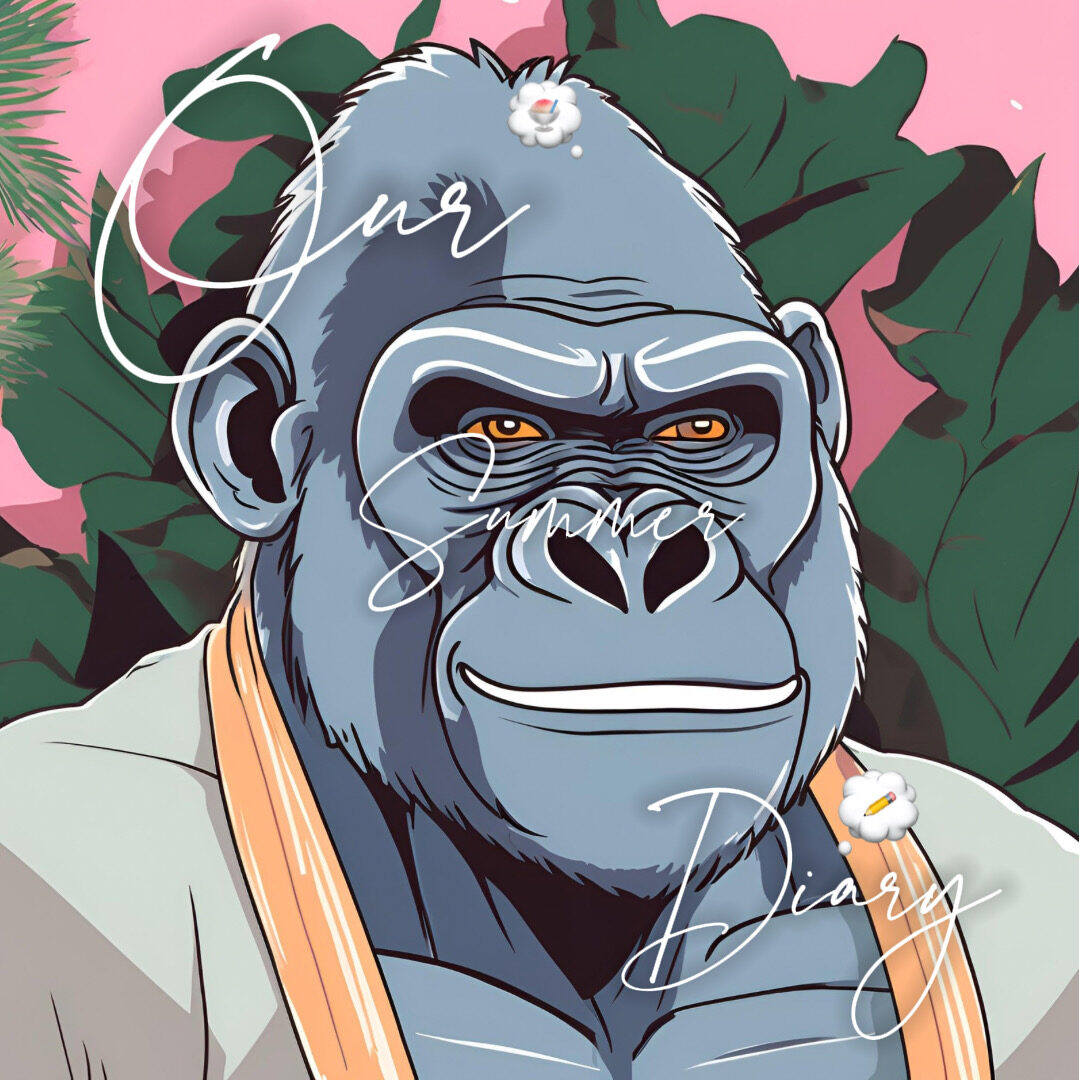夏休みなどの長期休業明けに学校へ行きたがらない子どもがいます。親としては心配ですよね。「明日、学校嫌だなあ」などと言われるとドキッとしますよね。不登校の始まり?…と心穏やかに過ごすことができません。我が子に限って…と思いつつも、友だちと何かあったのか、先生と何かあったのか、何か我慢し続けてきたのか等々、心配を張り巡らせます。
心理的に不適応を起こしていることは間違いないでしょう。
でも前述したように、問い詰めるのは少し待ちましょう。サポーターとしての大人が先行しては、主役は本当の気持ちを出しそびれてしまうかもしれません。
ここでは「不登校」の是非を伝えたいわけでわけではありません。
リアルにライブに動き続けている「子どもの心理」「子ども事情」に耳を傾けてほしいのです。現象に振り回されるのではなく、言動に焦りすぎるのではなく、一呼吸して寄り添ってほしいのです。
大人の仕事がそうであるように、休み明けに学校へ行くことが億劫になったり、少し長い休みが続くと教室へ出向くこと自体に勇気を要するものです。ただの怠け癖ではないのかもしれません。「今まで馴染んでいた環境が目新しく変化しているかもしれない」「友だちだったと思っていた友だちが友だちじゃなくなっているかもしれない」…
月曜日が「ブルーマンデイ」と言われるのと同じように、9月は「ブルーセプテンバー」などと言われることがあります。質問やあおりの追及をするのではなく、少しだけ遠巻きに且つていねいに観察し、必要があれば傾聴し、エールを送ってあげてください。
自分軸ではなく相手軸で
先生を含む大人は時折忘れがちになってしまうことがあるようです。
大人同士ではしないであろう無礼失礼を、子ども相手だとしてしまうことが…
なぜでしょうね。
その根っこに「育ててあげなくちゃ」「相手は人生経験不足」…
子どもからしたら当たり前でしょ。生まれてきた順番が違うのだから。でも同じ尊い命でしょ。