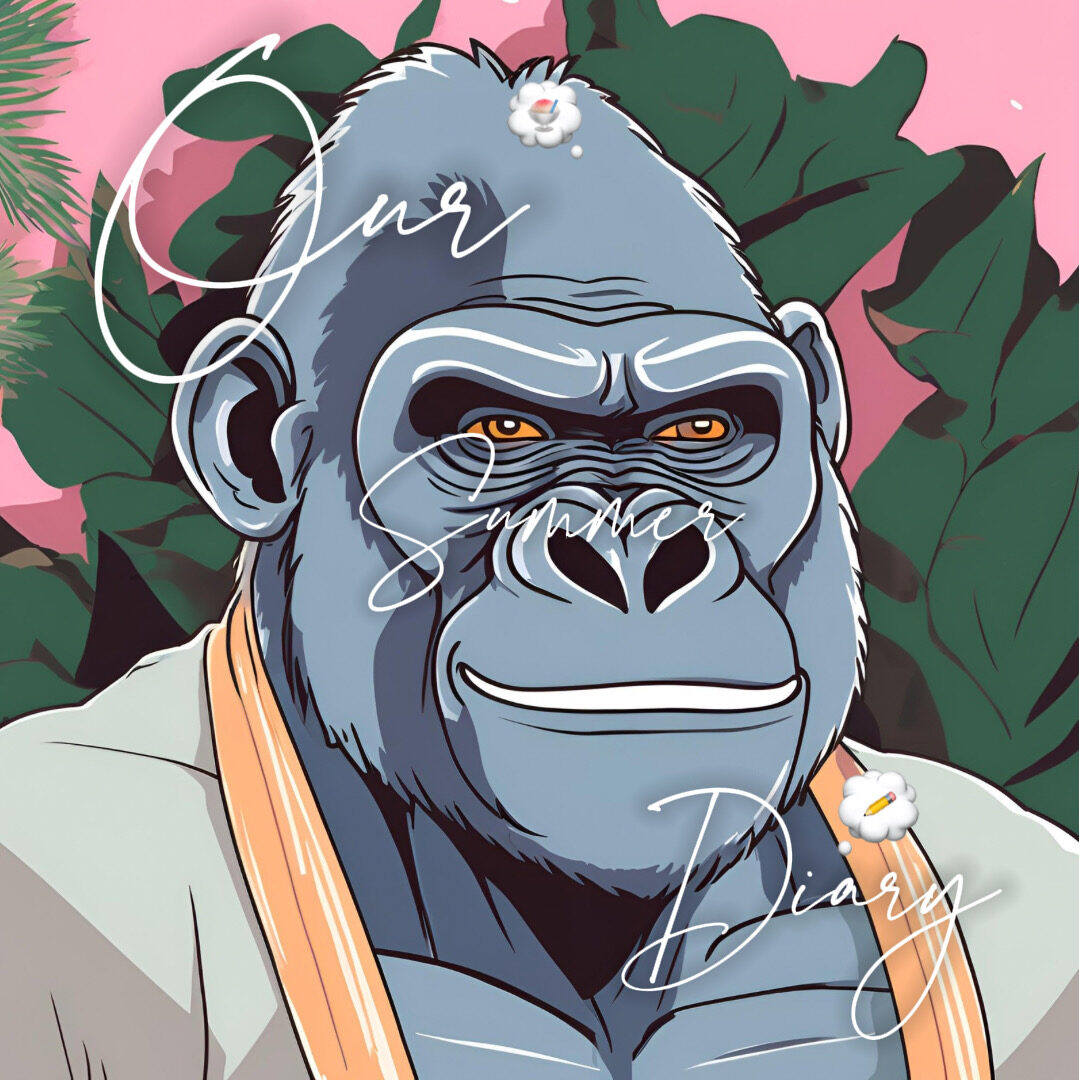兄(小6)弟(小5)妹(小3)、ご両親の5人ご家族。
小6のお兄ちゃんが4年生の頃から学校での不適応を起こし、登校渋りに…。学校もあの手この手で登校復帰を目指す。もちろんご家庭も原因探しとともに混乱、焦燥感を持たれるが、一向に本人の登校渋りは止まらない。「理由は?」…返答は「なんとなく。」「自分でもわからない。」…そうですその通りです。いじめがあるわけではない。先生との関係が悪いわけでもない。…理由を言語化できないのです。
さてその場合、大人の出番ですよね。言語化できない「なんとなく」の背景を見立てること。可能性を探ること。決して犯人探しに必死になってはいけません。可能性のある見立てを共有して、ご家庭と学校がより適切な支援のプランニングを立てることが重要です。
大人優位先行の見立て(アセスメント)や手だて(プランニング)ではいけません。ゆっくりじっくり落ち着いて耳を傾けること、観察することが大切です。主役は子ども。必ず不適応を起こさざるを得ない起因はあるはずです。
聴覚過敏によるしんどさ、周りからの視線に対するストレス、先生の指導が全て自分への𠮟責に受け止めてしまう過敏、教室の匂いに対する臭覚過敏、校舎の大きさに対する恐怖心、通学経路にある何かしらの不安、行事に対する不安等々、挙げようとすると限りなく可能性はあります。
そのお兄ちゃんの場合(小6)の場合、過程の中で医療でASDの診断を受け、より適切な支援計画の中で、現状は「登校刺激を避けましょう」ということになり、私のところへたどり着きました。保護者とのカウンセリングを経て、本人との面談、三者面談を通じて通所することになりました。
通常の登校時間と下校時間を避けるため、10時~15時までいつ来てもいつ帰ってもいいシステムを作って一定のカリキュラムを設定知っています。その子は、現在、毎日フルに通室して学習と他者との関わりに時間を有意義に活用してくれています。
さて、3年生の妹さん。小学校入学時にお兄ちゃんが家にいる状態。学校へ行く動機が上がらず登校渋りへ。
我々は二次障がいとして、その子どもが表出せざるを得ない現象(不登校やいじめ、暴力行動、自傷行為、非行等)をアセスメントする際、必ず家庭背景や養育歴(もっと言うと保護者の方の特性や養育歴まで)も見させていただきます。もちろんカウンセリングの中で許可を得て、個人情報厳守の範囲でですが。
学校のアセスメントは、兄に引きずられての全欠不登校というものでした。もちろん、ほぼ会ったことが無いお子さんの見立てですから、過程要因が先走るのも当然です。しかし、私が面談させていただいた結果、発達の特性(ADHDとASDの共存)を感じました。私は、WISCは出来ますが、医師ではないので診断はできません。だからこそ機関連携がとても重要となるのです。単機関(家庭・学校)は抱え込んで完結しないことがとても重要というわけです。
ご両親にフィードバックする際、発達の特性についてお話しました。
すると、ご両親もその点について可能性を疑っておられ、今後どうしたらよいのかを悩んでおられたとのことでした。。。その後、私から選択肢を頭のテーブルに乗せた上で、それぞれのメリット・デメリットをお伝えさせていただき、ご両親で話し合われた結果、一歩前へ進むことが出来ました。
因みに、現在、妹ちゃんも我々のところへ登録され、楽しく活発に過ごすことが出来ています。
その時、その安心が得られた前提で、はじめて今後どのように支援していくことかが考えられます。
「この子にとっての最善の利益か」を協議することができると思います。