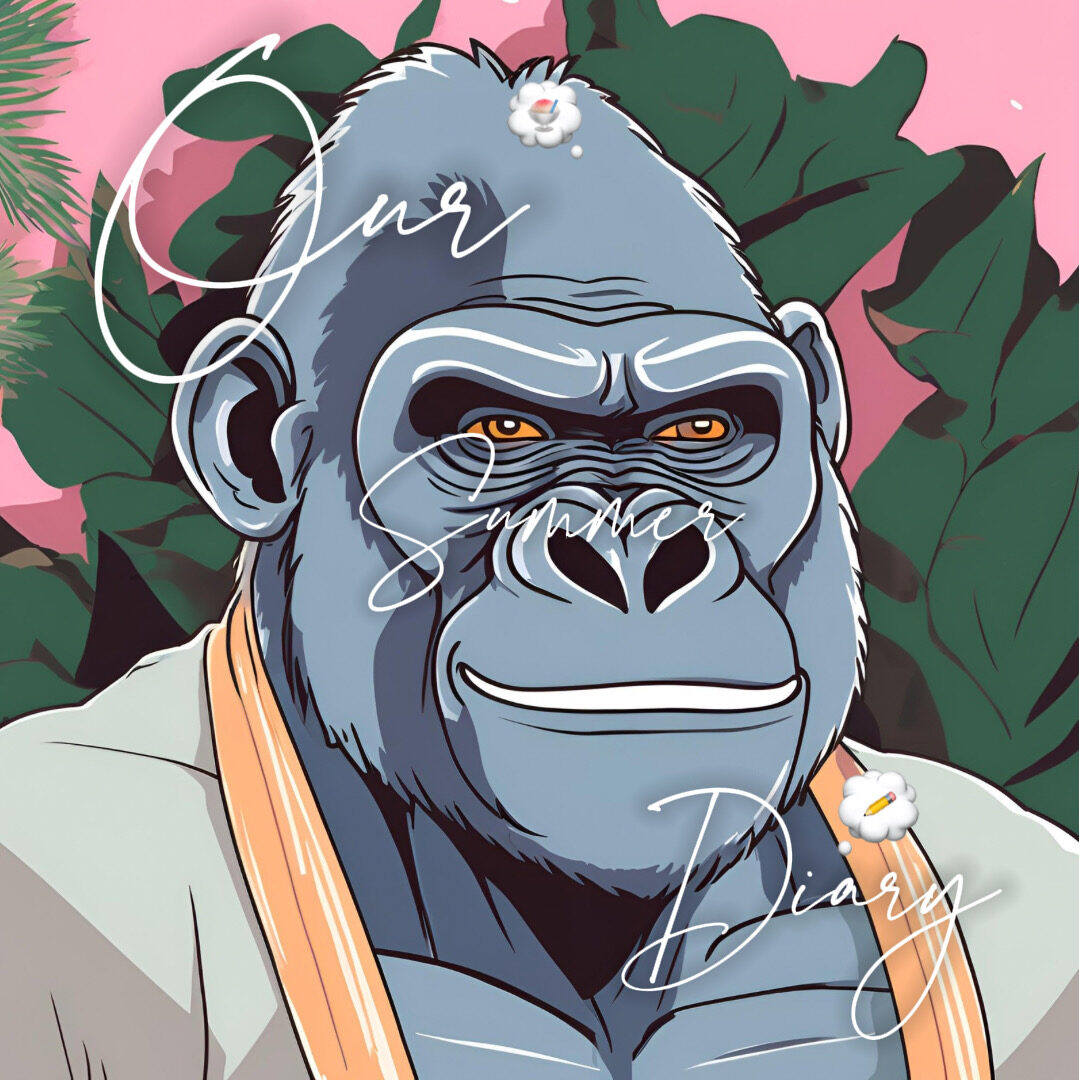「安心して十分に教育を受けられる学校環境」…
きれいな言葉ですね。でもとても難しいことです。そもそも「安心」が得られているのであれば、みな学校へ行きますよ。ではなぜ不登校状態になっているのか?そうならざるを得ないのか?そこを抜きにして「これだけの環境があるんだから。」「これだけサービスしているんだからこっちを向いてよ!」と言っても土台無理な話ですよね。
鶏が先か卵が先かじゃありませんが、「要因は子ども・家庭の中」とみている学校と「要因は学校の中」と捉えている子どや保護者とでは、折り合いがつかずとしても当然です。少なくても、養育歴や家庭環境、経済的側面において(大金持ちという意味ではなく)、習い事もお塾にも通わせてもらえたようなきれいな世界で生きた、そして現在も飲み食い困らず安定した生活を送っている先生に「救ってあげる精神」「俺の差し伸べている手なのに精神」は専らご免です。
失礼。
しかし、「本当の先生」は困っておられるはずです!!
偽善ではなく本気で向き合おう!!そして、この子の未来を!将来を!社会的自立を!18歳の誕生日の前日の姿を想像して「いまだからこそ自分に出来得ること、させていただけること」を真剣に考え努めていらっしゃる先生方も沢山おられます。というか誤解を解くために申しますが、年齢や経験、スキルの差異はあれども、ほとんどの先生方がそうであると信じています。ただ、組織の中にはそうではない人やサラリーマンのように(いや、そう言うとサラリーマンの方に失礼ですね)、「そこに出勤し、何となく滞在していれば安定したお給料がもらえる」「不登校の子どもよりもクラブ指導に生きがいを感じている」「若輩者なのに自己研鑽をしない」「退職金まであと何年かなあ」…等々…。ただでさえ安定している身分なのに世間知らずに「権利だ!主義だ!主張だ!」と叫ぶ、先生?という職業に踏ん反り返っている人が存在するのも事実です。
学校の中に潜む害となる人は皆、「相手軸」じゃないんですよ。すべてが「自分軸」なんです。
公教育ですよ。そこに身を投じ仕えている「全体の奉仕者」ですよ。
先ほど、「先生も困っている」…と述べたのは、「相手軸で真剣に努めている先生」です。当然ですが、ご自身の出産や育休、ご病気や介護等々、先生方も人間ですので勤務時間等についてはご配慮願いたいです。
組織の中のみならず、子どもや保護者の価値観や将来を勝手に分かったように語るような教師人生を送っていらっしゃる身の程知らずの上から目線の先生!…そんな先生に限って「あの子は困った子」「あの親は困った親」等々…はい!?…本当に困っているのは、「学校に不適応を起こしている子どもや保護者ですから!!」ついでに言わせていただくと、あなた方と同じような目で評価されるこちら側なんですけど。…批判してもダメなんですそういう人たちは…根っからのマインドが自分軸なのですから。
話が逸れたようですが、実は逸れてはいないんです。
つまり「環境」とは校舎や教室、机や椅子、トイレ、校内教育支援センター、保健室…等々のハード面のことではないと私は思っています。もちろん、より新しくきれいで別室もきちんと用意されている。これらもとても重要なポイントです。しかし、本当の「環境」とは、結局「人」なのです。
子どもにとって最も大切なことは「人との関わり」です。大人がそうであると同じように、合う人もいれば合わない人もいて当然です。だからこそ国や自治体には、より多くの「教育に人(予算)」を付けていただきたいのです。SCやSSW等の専門家活用もとても大切だと私も思います。しかし、目立つ、際立つ、宣伝になる専門家さん方(非正規雇用)を採用して、「教育にお金使っています!」みたいなのより、「将来有望な若手教員」を覚悟を決めて正採用し、ていねいに育成して、未来の宝である子どもたちに投資してください!!お年寄り教師の退職金予算計上の怖さに、宣伝広告の目くらませや明日にでも首切りができる非正規採用の講師を大量に利用しないでいただきたいです。
当たり前ですが、子どもや保護者の方々からしたら「学校で勤めている人はみんな先生(正採用・免許あり)」と思いますよ。勿論、非正規採用や免許なしの職員方々を否定しているわけではありません。それどころか、よほど一生安定に踏ん反り返る教員より有難いことの方が実は多いのですが…。残念。
「人は人との関わりの中でしか成長できない生物」です。相互作用です。
「オンライン授業しましょう。FAXでの学習支援。アバターでいいので出席扱いにしますよ。」…!?…諸々…それがこの国がかける不登校状態にあるの子どもへの教育機会確保及び環境整備ですか。